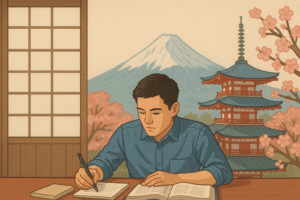特定技能外国人を採用する方法とは?企業が知るべき手続きと成功のポイント

深刻化する人手不足に直面する多くの企業が、即戦力となる人材を確保する手段として注目しているのが「特定技能外国人の採用」です。2019年に制度が創設されてから、実務面での改善が繰り返されており、2025年4月には運用上の大きな見直しが行われました。企業にとっては、よりスムーズに採用から受入れまでのプロセスを構築できる絶好のタイミングです。
本記事では、行政書士としての実務経験をもとに、特定技能外国人の採用フローを詳細に解説します。採用計画の立案から受入れ後のフォロー体制の構築まで、すべてのステップを体系的にご紹介し、読者が自社でスムーズに制度活用できるよう導いていきます。
特定技能制度とは?2025年改正ポイント
特定技能制度は、一定の技能水準と日本語能力を有する外国人労働者を日本国内で就労させることを可能にする在留資格制度です。対象となる分野は、介護、建設、農業、宿泊、外食、自動車運送業など16分野に及び、いずれも日本人の採用が困難な状況にある産業です。
2025年4月の制度改正により、手続面が大幅に簡素化されました。これまでは、四半期ごとに提出が求められていた「受入れ活動状況報告書」と、支援実施に関する届出が、一本化され、年に1度の提出で済むようになったのです。この変更により、事業者は報告業務にかかる事務負担を大きく軽減できます。
また、所属機関の適格性を確認する書類についても、原則年1回の提出でよくなり、継続雇用の際にも柔軟に対応できるようになっています。制度の運用がより実務に即した形となったことで、これから初めて外国人を雇用しようと考えている企業にも導入しやすい環境が整ったと言えるでしょう。
特定技能外国人を採用するメリットとリスク
特定技能外国人を採用することには、さまざまなメリットがあります。まず、一定の技能と日本語能力が証明された人材を雇用できるため、即戦力としての活躍が期待できます。採用にあたっては、技能評価試験や日本語試験( N4以上)を通過しており、一定の基準をクリアした人材が集まります。
さらに、特定技能1号から2号への移行要件を満たせば、家族の帯同が認められ、生活基盤の安定にもつながるため、長期的な雇用や職場定着が期待できます。
ただし、制度を運用する上ではいくつかのリスクも存在します。
- 支援体制が不十分な場合、外国人労働者が孤立する恐れがあります。
- 言語や文化の違いから、職場内での意思疎通が円滑に進まないことがあります。
- 申請書類の不備や制度違反により、在留資格が認められなかったり、企業が罰則対象となったりするリスクもあります。
これらのリスクに備えるためには、事前に社内での支援体制を整え、登録支援機関と連携することが重要です。また、行政書士など専門家による申請書類のチェックを活用し、正確かつ迅速な対応を行うことが求められます。
採用フロー全体図(国内・海外在住者別)
特定技能外国人を採用する際の流れは、次のような6つのフェーズに分けて考えることができます:
- 採用計画の立案
- 人材の募集・選定
- 雇用契約の締結と支援体制の構築
- 在留資格申請
- 入国後のフォロー
- 継続的な管理
それぞれのステップは、候補者が日本国内に在留しているか、海外に居住しているかによって異なる準備が必要です。
たとえば、国内に在留している技能実習2号修了者などは、在留資格変更許可申請のみで対応可能です。
一方、海外からの採用の場合は、在留資格認定証明書(COE)の取得から始まり、ビザ発給、航空券手配、入国後の対応といった複数の工程が必要です。おおよそ3か月から半年程度を見込んでスケジュールを組むのが一般的です。
このように、採用対象者の現在地や在留状況に応じて、適切な手続きを把握し、段取りよく進めることが成功の鍵となります。
STEP1 採用計画策定と社内体制整備
まずは、どの部署にどのような人材が必要かを明確にするため、職務内容や配置先、業務範囲を整理します。このとき重要なのが、「同等報酬の原則」です。これは、日本人が同一の業務を行う場合と同等以上の待遇を用意しなければならないという制度上の要件です。
次に、外国人を受け入れる体制を整備する必要があります。コミュニケーションの取り方、宗教上の対応、文化の違いの理解など、特定技能外国人が安心して仕事ができる環境づくりをすることが重要です。
必要に応じて、社内マニュアルの整備や受け入れ体制の研修も実施しておくと、スムーズに進みます。
STEP2 人材募集・スクリーニング
採用計画が定まったら、次は実際に人材を募集します。募集の方法にはいくつかあり、状況に応じて適切な手段を選択します。
主な募集ルート:
- ハローワークや求人媒体の活用
- 登録支援機関ネットワークからの紹介
- 海外の送り出し機関を通じた現地採用
面接時には、以下の点を確認するとよいでしょう。
- 技能試験や日本語試験の合格証を提示できるか
- 過去の職歴と希望業務との整合性
- 日本での生活に対する理解と適応力(住居、食文化など)
- 社内との円滑なコミュニケーション能力
単なるスキルだけでなく、文化的なフィット感や生活力も見極めることが、採用後のトラブル防止につながります。
STEP3 雇用契約の締結と支援体制の構築
候補者が決定したら、次は雇用契約の締結に進みます。特定技能においては、契約書の内容にも一定の要件があり、日本人労働者と同等以上の報酬や労働条件が求められます。契約内容を理解してもらうため、入社前に母国語での説明も必要です。
雇用契約のポイント:
- 契約期間は原則1年更新。(特定技能1号の在留資格は1年更新)
- 報酬、勤務時間、残業代、福利厚生の記載が明確であること
- 外国人本人が理解できる言語で事前ガイダンスを行う
また、外国人労働者の生活支援を行う「支援計画」の策定も必須となります。これには、生活ガイダンス、住居支援、日本語学習機会の提供などの支援項目が含まれます。自社で実施する場合は支援責任者の配置が必要となり、外部の登録支援機関に委託することも可能です。
STEP4 在留資格申請(認定または変更)
雇用契約が締結され支援計画が整ったら、出入国在留管理庁への申請に進みます。手続きの種類は以下のとおりです:
- 海外在住の候補者 → 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
- 日本国内在住の候補者 → 在留資格変更許可申請
必要書類は多数ありますが、特に以下の書類は正確な記載と証明が求められます。
主な必要書類:
- 雇用契約書
- 健康診断書
- 支援計画書
- 技能試験・日本語試験の合格証明書
審査には通常2~3か月程度かかるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。書類不備があると差し戻しや再提出の必要があるため、専門の行政書士に依頼することで、申請をスムーズに進めることができます。
STEP5 入国後のフォローと生活支援
許可が下りた後、外国人が日本に入国すると、企業側には受け入れ体制を整える義務が生じます。まずは空港での出迎えや住居の手配、ライフライン契約の支援が必要です。登録支援機関に支援を依頼している場合は、登録支援機関が対応してくれます。
入国後1週間以内に行うべきこと:
- 住民登録・マイナンバー取得
- 健康保険・厚生年金の加入
- 銀行口座開設、携帯電話契約
- 職場オリエンテーション(労働条件や安全管理の説明)
さらに、定期面談を実施し、職場や生活に適応できているかを確認することが義務づけられています。
STEP6 継続的な管理と更新手続き
在留期間は原則として1年ごとの更新となっており、期限満了の3か月前から更新手続きが可能です。また、2025年4月の制度改正により、受入れ活動状況や支援実施状況に関する届出が、年に1度(4月〜5月)に一本化されました。
定期的な対応項目:
- 年1回の届出書の提出(受入れ・支援状況)
- 在留資格更新の準備(契約更新、支援計画の再確認)
- キャリアアップ支援(特定技能2号への移行希望者には熟練技能試験の情報提供)
継続的なフォローを行うことで、外国人労働者の定着率も高まり、企業にとっても長期的な戦力となります。
まとめ
特定技能外国人の採用は、単に「人材を雇う」というだけにとどまらず、制度的な理解、社内体制の整備、法令遵守、文化的配慮など、多角的な準備と継続的なフォローが求められるプロセスです。
しかし、その分しっかりと制度を活用すれば、安定した即戦力を確保できるだけでなく、外国人材の定着や企業全体の国際化推進にもつながります。
採用までの道のりは決して短くはありませんが、一歩ずつ丁寧に進めることで、長期的に信頼できるパートナーとしての人材を育てることができます。